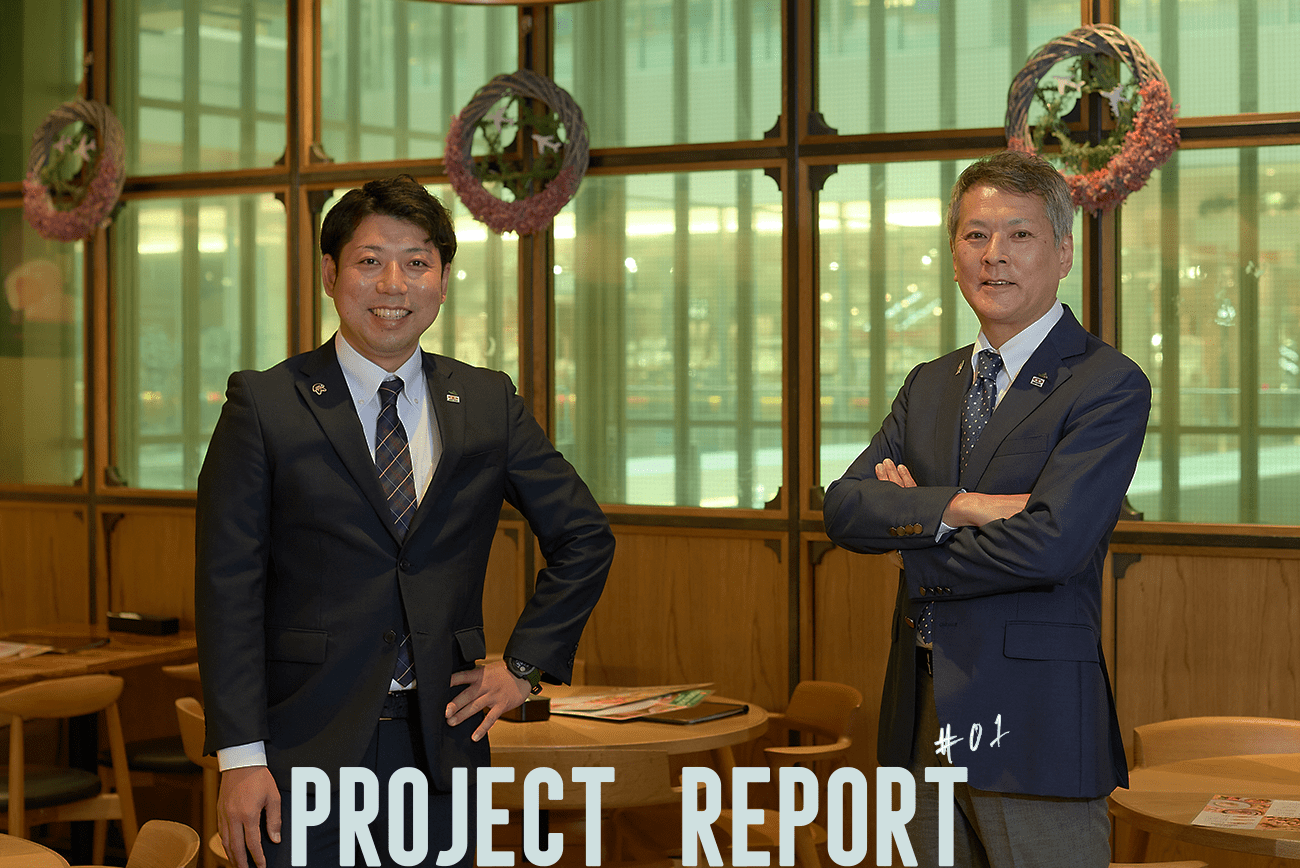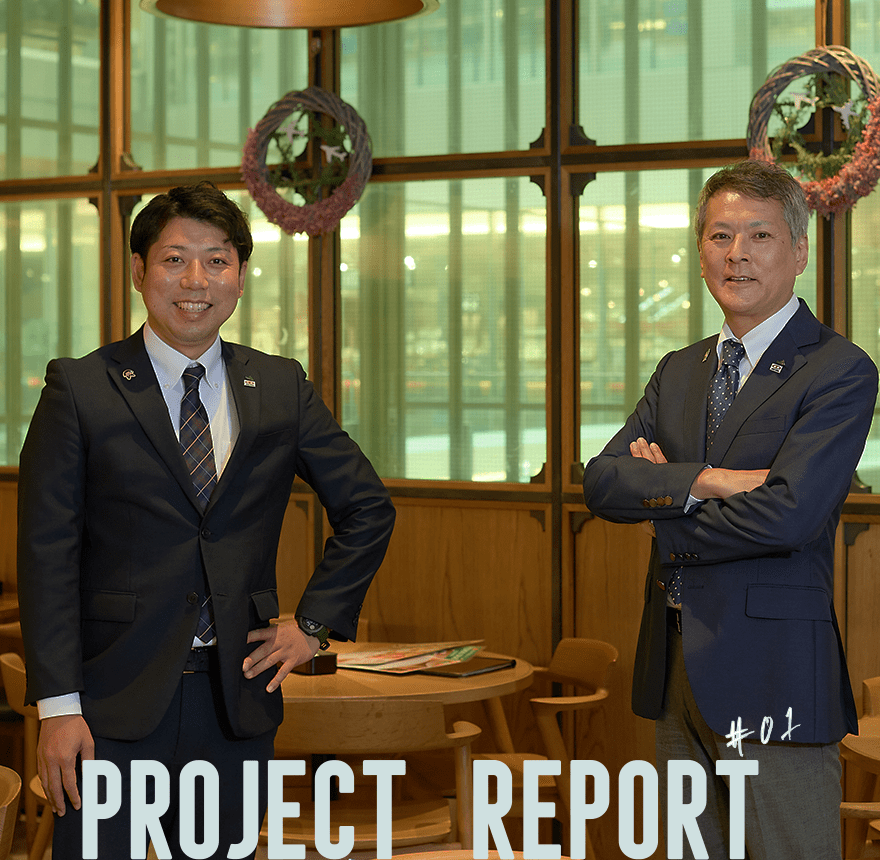柴田 温
Atsushi Shibata
1989年入会
農学研究科修了
本所
耕種総合対策部
東北営農資材事業所
研究職として入会し、営農・技術センターの商品開発研究部において、鮮度保持技術開発、米や飲料商品開発、官能評価手法、機能性食品の開発などに従事。そして2000年、大消費地販売推進部に異動し、全農安心システムの企画・推進を担う。続いて、営農・技術センターや営農販売企画部で室長や課長を務め、2014年に総合企画部震災復興課課長に。その後、営業開発部次長を経て、2018年より現職。

佐藤 智明
Tomoaki Sato
2007年入会
工学資源学部卒
秋田県本部
管理部
企画管理課
秋田県の兼業農家の家に生まれ、周囲は田んぼだらけの環境で育ち、農作業を手伝うのが当たり前だった。大学は工学部に進学したものの、地元で就職したい、慣れ親しんだ農業に関わる仕事がしたいと入会。入会後は秋田県本部の生産資材部で肥料農薬を、続く管理部で経営管理や広報を担当し、2013年に本所へ異動。経理部、経営企画部の業務に従事し、2018年より現職。本プロジェクトのメンバーに。
東北6県がひとつになって、何か新しい事業ができないか。
JA全農では現在、若手職員が中心となり、そこに中堅・ベテラン職員が加わることで、大小さまざまなプロジェクトが進められている。なかでもユニークな取り組みとして、着実に成果を上げているのが「全農東北プロジェクト」だ。その特徴をプロジェクトメンバーのひとり、秋田県本部の佐藤は次のように解説する。
「従来のプロジェクトは、本所と県本部がタッグを組み、タテのつながりのもとに進められるものがほとんどでした。対して本プロジェクトは、はじめから東北6県の県本部がヨコのつながりのもとにスクラムを組み、本所の機能を活用して進めているのがポイントです。そして目指しているのは、東北のファンをつくり、東北に来てくれる人を増やすこと」
プロジェクトが動き出したのは2014年。広く社内よりアイデアを募集する「新規事業提案制度」を通じ、岩手県本部の若手から寄せられたアイデアがきっかけだった。「東北6県がひとまとまりになって、何か新しい事業ができないか」——。しかし、この時点では企画が進まなかった。
とはいえ、「その発想やよし」。いきなり事業化は難しくとも、プロジェクトとして立ち上げる価値は十分にある。役員とともに、その可能性に注目したのが当時、本所の総合企画部に在籍していた柴田だった。柴田は震災復興課課長として、震災復興、生産振興、東北地区ブランド化支援に向け、前線で陣頭指揮を執っていた。これまでの豊富な業務経験を踏まえ、柴田は東北地方について次のように語る。
「日本の社会課題は地方から進んでいく。とくに東北地方は顕著ですね。高齢化や過疎化は進む一方だし、各都市間の距離が離れているうえ、冬は雪に閉ざされてしまうことから、他の地方と比べても東北地方は地域間の交流が少ない。結果、活力は失われていくばかりですが、こと農業から東北地方を見渡すと別の景色が見えてきます。北の青森から南の福島まで、各県には全国に知られる名産品がある。加えて、東北地方の食糧自給率は100%を優に超え、6県を合わせると米、肉、野菜、果物と、農産物のほぼすべてを網羅し、その生産量は日本最大です」
しかも、東北6県すべてが海に面していることから水産物も獲れるし、東北地方を貫く奥羽山脈は森林資源の宝庫でもある。つまり、東北地方は独立国家、サステナブルな国家として歩んでいけるほどのポテンシャルを有しており、本プロジェクトを通じて「東北のモノを売る」「東北にヒトを呼ぶ」ことを実現できれば、地方創生、地域活性化へとつながり、東北地方で顕著な社会課題の解決を一気に図っていくことも決して不可能ではない。
実は本プロジェクトは、これからの取り組み如何によっては、それくらいのインパクトを与えていける夢のあるプロジェクトなのだと、柴田は言葉をつなぐ。

プロジェクトを通じ、インナーブランディングにもつなげていく。
柴田は早速、プロジェクト立ち上げへと動き出した。6県の県本部へと足を運び、各本部長に直談判。「気鋭の若手を送り込んでほしい」と依頼した。それというのも、柴田には思惑があった。本プロジェクトはインナーブランディングに活用できる。つまり、既成概念や固定観念から自由な若手を通じて、組織内の意識変革、文化改革を促せると考えたのだ。
それというのも農業というのは気候・風土に大きく左右される産業であるため、地域性が強い。JA全農が32都府県に県本部を構え、地域に応じた取り組みを進めているのも、それが理由だ。しかし、こうした体制で仕事をしていると、どうしても自分たちの県域のこと、自分たちの業務領域のことだけを考えた、縦割りの仕事となってしまいがち。そこで柴田は、本プロジェクトを通じて組織に「横串」を通し、若手をメンバーに任用することで、県本部間、部署間を横断した連携を彼らの手で生み出させ、若手たちが広い視野のもとに仕事をしていくことを企図した。
こうして各県本部長が指名した若手6名を主体に、柴田ら事務局メンバーを加えたプロジェクトチームが発足。まずはマルシェを企画し、最初は仙台で、続いて東京で、東北産品を販売し、他社が企画するイベントにも積極的に参画するなど、プロジェクトは〈プロモーション〉活動からスタートした。その狙いを、柴田は次のように明かす。
「いきなり会議を開いたところで、煮詰まって非生産的な時間ばかりが過ぎるだけ。それよりは実際に動きながら、東北の情報をしっかりと発信し、同時に地元での売れ筋、東京での売れ筋を確認する。そこで異なる売れ筋を示す産品、とくに東京でよく売れる産品があれば、そこにニーズがあることがわかる。つまり、マルシェを通じた〈プロモーション〉活動は、マーケティング・リサーチでもあるということです」
しかも、こうして行動を起こしていけば、必然的に横のつながりも生まれ、〈パートナー企業との連携〉の足掛かりとなっていく。そのことを最初に身をもって示したのも柴田だった。柴田はこれまでのキャリアから、東北観光推進機構とつながりがあった。同機構は観光を、東北で成長が見込める「戦略産業」と位置付け、東北地方の経済活性化を目指し、航空会社や鉄道会社、旅行会社などが協賛していた。観光と農業とアプローチは違えども目的は同じ。JA全農も賛同し、会員として名を連ねることになった経緯があった。
話はここからで、柴田は同機構を通じて、日本航空や全日本空輸の担当者たちに知己を得ていた。そこで彼らに本プロジェクトの立ち上げと、マルシェの開催から活動を始めた旨を伝えると、空輸の手配はもちろんのこと、空港から先の陸送の手配でも協力できるとの申し出を受けた。それまで宅配便を利用して開催していた仙台や東京でのマルシェは、柴田が航空会社の協力を取り付けたことで、一気に日本列島を縦断し、沖縄での開催が実現される運びとなった。
プロジェクトチームは、それまでのマルシェを通じて東北の大豆を用いた「大豆製品」、なかでも豆腐がよく売れることをつかんでいた。そこで固い島豆腐が県民食となっている沖縄で、果たして東北産の豆腐がどこまで売れるか試してみたところ、即完売の売れ行きを示した。東北産品として今後、注力すべき商品のひとつが、ここで明らかとなった。
一連の出来事は、柴田に言わせれば最初の一歩に過ぎなかった。ただ、各県本部から集まった6人の若手メンバーたちには、自分たちがこれからプロジェクトを通じてどういう活動を展開していけばよいかをイメージさせるには十分すぎる成果だった。そしてここから、若手たちによる快進撃が始まった。

銘柄米を詰め合わせたヒット商品「東北六県絆米」の本当の価値。
2018年に本プロジェクトに配属された佐藤は、「事務所にこもっていても何も始まらないことを理解し、柴田さんたち事務局が有する人脈のつながりを活用させてもらいながら、活動の輪を広げていった」と振り返る。
たとえば〈プロモーション〉においては、日本航空の協力を仰ぎ、東北出身の客室乗務員にもプロモーション活動に加わってもらった。その後はコロナ禍で客室乗務員たちも乗務数が減ったこともあり、強力なパートナーとなってくれた。日比谷花壇と連携した「東北のお花を飾ろうプロジェクト」も、彼女たちの企画により立ち上げられたものだった。また、佐藤たちは外部企業とのキャンペーン連携を通じた商品PRを企画。サントリー商品のキャンペーンに協賛し、賞品プレゼントに東北県産品を提供することで認知度を高めていった。
また、〈パートナー企業との連携〉では、先の東北観光推進機構とインバウンド集客や東北デスティネーションキャンペーンを展開。東北七新聞社協議会とは、フォーラム参加、イベント開催、SNSからの情報発信といった連携を行っている。さらにユニークなところでは、仙台スイーツ&カフェ専門学校ともコラボレート。ここには柴田ら先輩たちの知見を活用させてもらったと、佐藤は話す。
「『みのりみのるプロジェクト』における飲食店のスタッフさんたちがそうであるように、東北の食材、産品を広めていくには『語り部』が不可欠であることを知りました。そこで私たちも、同校の生徒さんたちに語り部となってもらおうと考えました。農業実習の場を提供するとともに、授業の一環として行われる東北地方の食材を用いたメニュー開発において、これぞと思うものは期間限定で仙台にある『みのりカフェ』のメニューとして展開していますし、場合によっては商品開発にも活かしていきたいと思っています」
ちなみに、その〈商品開発〉では、前述の東北産大豆商品の開発とブランド化を推し進める一方、地元飲食店と連携し、東北産食材を使用した「とうほくサラダ」を各飲食店で販売。また、東北産たまごの開発にも取り組んでいる。そして現在も、さまざまなプランを企画、実行している佐藤たちだが、実は本プロジェクトにおいても大きなターニングポイントになったのが、「東北六県絆米(きずなまい)」の開発だったと、佐藤は明かすのだ。

「東北六県絆米」とは、各県の銘柄米をワンセットにした商品だ。300g、約2合分の銘柄米を6種類詰め合わせたこの商品は、単身世帯の増加にともなう個食化が進んでいるという市場ニーズを満たし、ヒット商品となった。しかし、この商品は消費者に対してよりも、むしろJAグループ内部に対し、少なからぬインパクトを与えた。

長所を伸ばし、短所は相互補完することで、6県の個性を際立たせる。
佐藤は話す。
「東北地方の主要産業と言えば、農業や漁業といった第一次産業。それだけに良くも悪くも産地間競争が激しく、言葉は悪いですが隣県同士が潰し合っている側面があります。その最たる例が米です。もちろん、それがブランド化につながっているので、決して悪いことではありません。ただ、本プロジェクトを通じて私たちが思ったのは、日本人の『米離れ』が進むなかで、東北人同士が小競り合いをしている場合ではないということです」
6人のメンバーたちは想いを共有した。それぞれの県がプライドをもって個性を磨いてきた銘柄米だからこそ、それを6色の多彩な個性として全面に打ち出し、「日本米の実力、ここにあり!」というのを、われわれ東北から日本に、そして世界に示そうではないか。日本人の「米離れ」を食い止め、グローバルで日本食の素晴らしさを伝え、日本や東北に人を呼び込むためにも、東北6県銘柄米をこそ旗印にしようではないか。そうやって東北地方を活気づけるとともに、震災以降、復興に向け各地から寄せられた恩に報いるためにも、今度はわれわれが起点となって日本を元気にしていこうではないか——。
各県本部から集まった6人はあらためてスクラムを組み直し、県本部の所管部署の協力を取り付け、それぞれの地元JAを動かし、生産者の気持ちをひとつにしてリリースさせたもの。それが「東北六県絆米」だった。産地間競争は当たり前。隣県はライバル。自県の農業を振興させていくには、他県との競争に勝つ以外に術はない。そう固く信じて業務に励んできた各現場の職員たちは、その商品を見て口々につぶやいた。「こんなことができるのか」と。一連の取り組みを見届けてきた柴田はいう。
「キャリアを重ね、組織に馴染むほど、既成概念や固定観念にからめ捕られて自縄自縛に陥りがち。でも若手はそうではない。彼らに不足している経験は、人脈によって補填されるし、若いときに築き上げた社内外の『絆』は、お互いが組織内で偉くなったときに大きく物を言ってくる。だから私は、このプロジェクトに終わりはなくてもいいと思うし、東北活性化の取り組みを通じて、若手たちが人脈を形成する場になればと思っています」
柴田が語る内容は、さながら有志が研鑽を積む「道場」を思わせるが、その門下生とも言える佐藤もまた、次のように語るのだ。
「本プロジェクトを通じて私自身、他県の現場を目の当たりにすることで、自県をより深く知ることができました。ここでの気づきや課題は今後、さまざまな業務に活きてくると思っています。ただ、今後の秋田県の農業を考えたとき、私は他県と比べて弱点があってもいいのではないかと考えるようになりました。それというのも東北6県の連携があれば、他県の弱みを自県が補う、その逆も然りで、お互いが得意な分野を伸ばしながら相互補完することができます。こうした取り組みこそが、実は東北6県それぞれの個性を際立たせ、東北を訪れ周遊する楽しさを生み、東北のファンを増やし、東北のブランド力を高めることにつながっていくのではないか。今は、そんなふうに思っています」
そうやって東北6県がスクラム組んで、首都圏をはじめ全国に安心安全、かつ多彩な個性が宿る食糧供給の役割を全うしていきたい。いずれ本プロジェクトを離れても、ここで築いた人脈を足掛かりに、部署や県、企業といった垣根を越えて、その輪を拡大させながら、農業を起点に魅力ある地域社会づくりに貢献したい。そう、佐藤は言葉をつなぐ。そして相談に来る後進たちに伝えているのは、プロジェクトチームの合言葉だ。
まず東北からやってみよう!
(文中の企業名、敬称略)