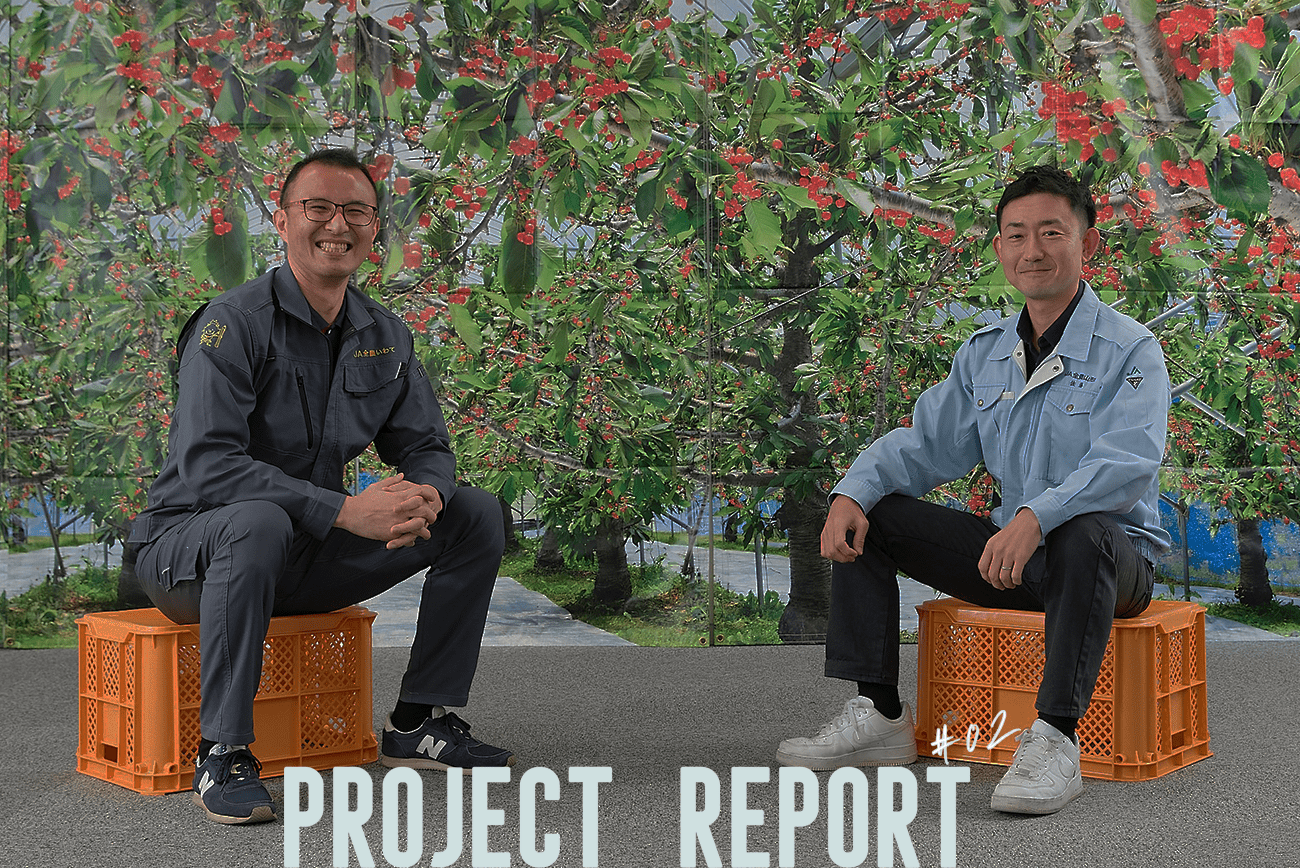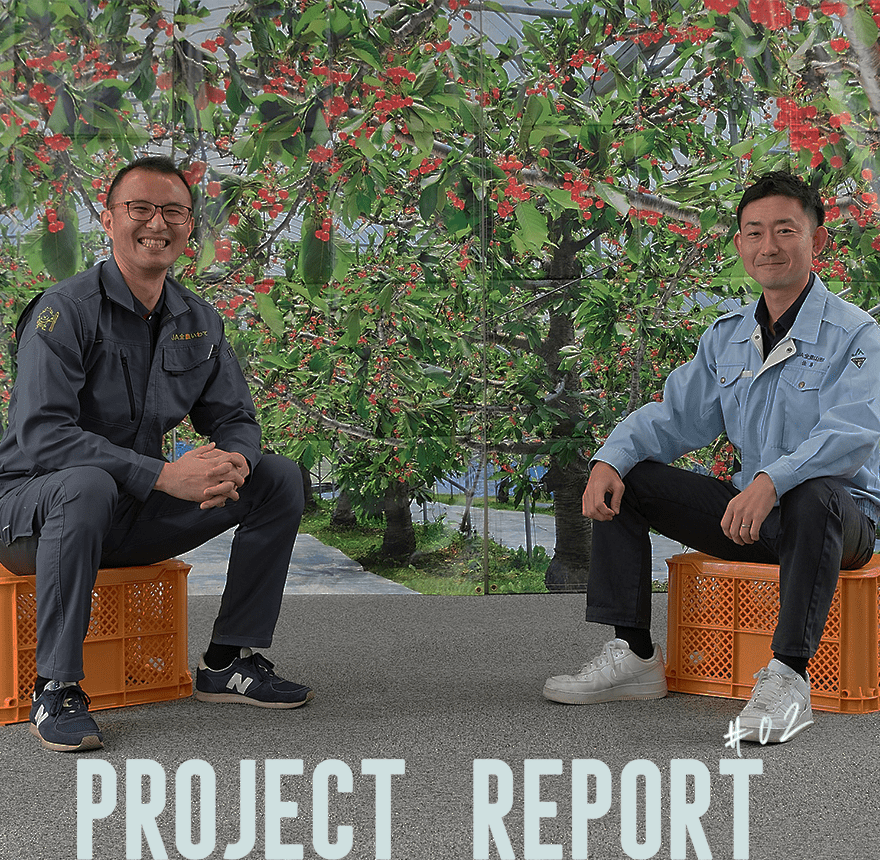早見 隆志
Takashi Hayami
1999年入会
農学部卒
本所
耕種総合対策部
TAC推進課
労働力支援対策室
栃木県の専業農家に生まれ、農業は生活そのものだった。農学部に進学し、農業に貢献できる仕事に就きたいと、栃木経済連(現・栃木県本部)に入会。園芸部、企画管理部を経て、全国域での仕事がしたいと思うようになり、2005年に県本部から本所へコース転換。青果センターを経て、2008年に耕種総合対策部に。以来、TACの活動支援、生産基盤維持拡大などの業務を行っている。2021年より現職となり、労働力支援強化などを通じた、社会課題解決を図っている。

佐藤 大輔
Daisuke Sato
2005年入会
農学部卒
山形県本部
営農企画部
営農支援課
大学時代は研究室生活を送っていたが、研究職や開発職よりも、多方面から農業に関わる仕事が性に合うと実感。地元山形を盛り上げたいと地方公務員も検討したが、地元を拠点に全国へ影響を及ぼす仕事ができることに魅力を感じて入会。総合企画部、生産資材部を経て、2017年に本所の東北営農資材事業所に。営農業務に従事するなかで、地元山形で労働力支援の企画を自らの手で実行したいと考え、2021年より現職。
生産者の負担を減らし、作業者も好きな日時に働ける仕組み。
少子高齢化を背景にした労働力不足は、農業における積年の課題だ。農林水産省が発表している数値によれば、2015年には208万人いた農業就業人口も、2020年には160万人と、わずか5年で48万人も減少している。団塊世代の大量離農も目前に迫るなかで、後継者を確保していない経営体が7割に達しているとの気になる数値もある。農業就業人口の減少、農業における労働力不足は、この国の食糧事情を大きく左右するだけに、JA全農もこれまでにさまざまな労働力支援を行ってきた。
たとえば、県や組織を越えた労働力支援に関する情報共有・コミュニケーションの場としての「ブロック協議会」の設置拡大、先行事例の情報発信や蓄積による「水平展開」、WEB求人サイトの導入をはじめとした「マッチング強化」、営農管理システム(Z-GIS)を核とした「作業軽減につながるツールの推進」などだ。近年は、障がいを持つ人たちを生産現場に受け入れる「農福連携」も推進している。
こうした各種取り組みのなかでも、とくに力を入れて取り組んできたのが「農作業請負の仕組みづくり」だ。なかでも大分県は、農業就業者の平均年齢が全国のそれを上回り、早くから労働力不足の問題が顕在化していた。そこで大分県本部は、この問題の解決にいち早く着手し、農作業を請け負うパートナー企業との連携を実現させ、大きな成果を収めてきた。現状では延べ人数にして年間約2万人もの働き手を、農業の現場へと投入できるまでとなった。大分県本部の取り組みについて、早見は次のように解説する。
「これまで人手を必要とした生産者は、自分で雇用するか派遣会社に依頼するかしか方法がありませんでした。また、作業者にとっても、常時雇用となるためフレキシブルな働き方が難しく、それが農業の現場で働くハードルにもなっていました。しかし、生産者が請負会社に作業を依頼することができれば、作業指導は請負会社が担うため、生産者は別の作業に専念できますし、支払いも出来高払いとなります。作業者にしても、出勤希望を踏まえたシフト制で働くことができるので、これまで農作業に興味を持っていても、それを果たせなかった人も好きな日時に働くことができます」
こうしたメリットがあるだけに、早速にでも全国に水平展開したいところだったが、大分の請負会社は地域に根ざした企業であるうえ、いきなりの全国展開は現実的ではなかった。かといって、都道府県ごとに一からパートナー企業を探していては、効率も悪く、全国レベルで展開した際の全体最適も図れない。こうしたなかで2021年、タッグを組むことに名乗りを上げてくれたのが、旅行業界最大手のJTBだった。
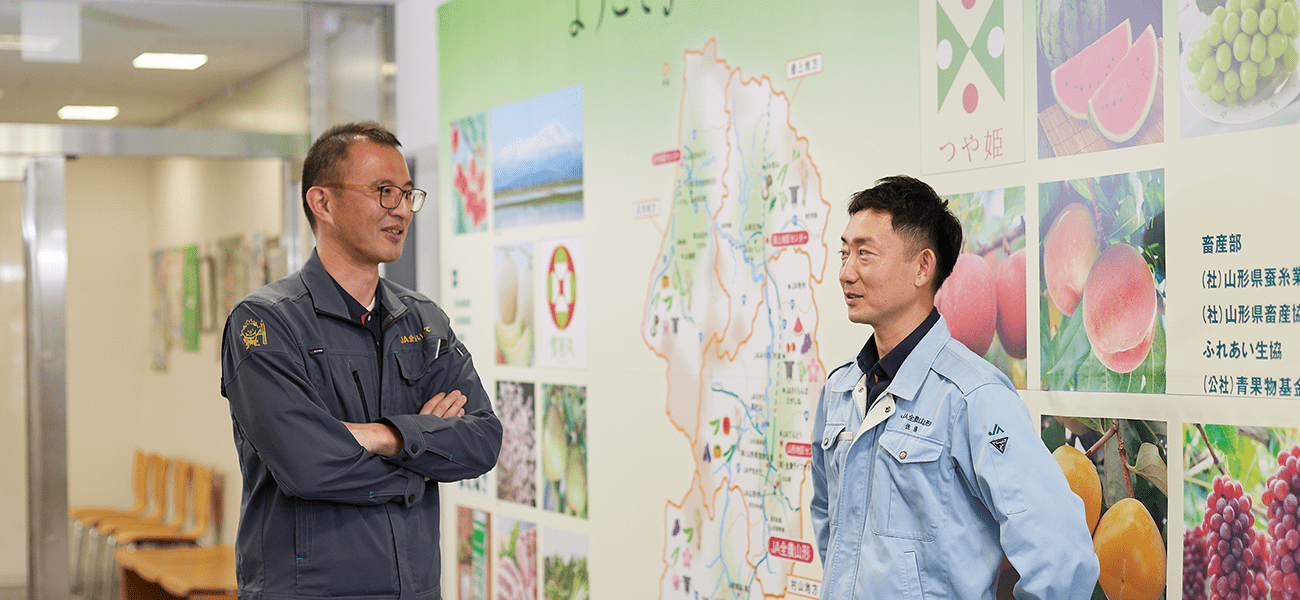
機械化が図れず、慢性的な人手不足に悩む山形で試験導入。
早見は、JTBとの連携は自分たちにとってメリットしかないと話す。その理由は、次のとおりだ。
まずJTBは全国に支店網を持っているため、全国レベルでの連携が可能であること。加えて、従来の観光事業で培ったノウハウとネットワークを有し、提携宿泊施設や交通機関などの観光業をはじめ、関連地元企業、経済団体、教育団体など、多様なコネクションから地域の人材の手配が可能なこと。そして将来的には、JTBを通じた宿泊施設への食材供給や土産物販売など、国産農畜産物の消費拡大と、地産地消による地域経済の活性化も期待できること。まさにJTBは、最強のパートナーと呼ぶに相応しい存在なのだ。
また、両者が知見やノウハウをしっかり共有することではじめて、全国への水平展開、スムーズな作業実施が実現されるのだという、早見たちの本気と覚悟がここには込められている。そして、いの一番に手を挙げ、現場への試験導入を成功させたのが山形県本部の佐藤だった。
「実は私も本所在籍時に大分県本部での先進事例について研究するなかで、山形にこそ必要な取り組みであると確信しました。ご存知のとおり、山形はさくらんぼにはじまり、ラ・フランスや桃、ぶどうといった果樹の栽培が盛んですが、いわゆる園芸農業というのは機械化が図りづらく、脚立に乗っての手作業が今も続いています。しかも、収穫時期というのが短期集中的に訪れるため、とくに、さくらんぼシーズンの人手不足は深刻で、それこそ行政や学校を中心に地域をあげて取り組んできたものの、いまだ解消にはいたっていません。それだけに是が非でも山形に導入、普及させたいと思ったのです」
佐藤は早速、JTBと連携し、さくらんぼ生産者3軒、ラ・フランス生産者6軒に対し、労働力支援を実施した。試験導入ということもあり、あらかじめ生産者を限定しての取り組みだったが、佐藤は作業時期、作業内容、作業人数などを生産者からヒアリングしては、その内容を随時、JTB担当者に伝えた。JTB担当者も、佐藤からの情報を参考にしながら、ニーズを満たせるだけの人手を確保すべく、取引先や関係先に声をかけ、県内居住者を対象に募集をかけていった。日頃から旅行の求人を業務としている人たちだけあって、広く声をかけるにしても、チラシをつくるにしても、その手際のよさは見事だったと、佐藤は振り返る。
とはいえ、佐藤にしてもJTB担当者にしても、「本当に人は集まるのか?」「予定通りに仕事はあるのか?」と、気が気ではなかったようだ。事実、予定していた収穫日の前日に天候が急変し、生産者から「明日は中止にさせてほしい」との連絡が寄せられたこともあった。佐藤たちはこうした不測の事態が発生するたびに、実行内容と結果をきちんと整理、記録し、今後似たような事態が生じた場合の参考事例として積み上げ、スムーズな運用を実現するため対応ノウハウを蓄積していった。
地道な取り組みだが、佐藤がこうして現場の記録やデータを細大漏らさず本所の早見へと報告する。早見は、そうして各県本部から送られてくる記録やデータを一本化し、エッセンスを抽出して方向付けをしたら、再び各県本部へと戻し、佐藤がそれを参考に実行へと移していく。まさにPDCAの繰り返しだが、これはJTBにとっても同様だ。こうして試験的な取り組みも、やがて仕組みとして洗練され、事業として拡大され、日本全国へと展開される。手間も時間もかかるが、仕事とはそうやって付加価値を付けていくものだということを、佐藤も早見も、そしてJTBの担当者たちも心得ていた。

この国のあるべき姿を描いたグランドデザインそのもの。
県内における初めての試みということもあり、実際の作業日には佐藤も一緒に農作業の輪に加わった。佐藤を驚かせたのは、作業員たちの年齢層の幅広さだった。今回の試験導入では、トータルにして延べ約650人の人が集まった。下は10代から上は70代まで、その多彩な顔ぶれが佐藤にはうれしかった。それというのも、「JAグループが伝手を頼りに人を集めても、結局は農業と接点のある地元の年配者がほとんどで……」と佐藤も苦笑いをする。ところが、JTBの力を借りれば、これまで農作業とは無縁の人たちまでもが、こうして集まってくれる。その様子も、まるで旅先のホテルでアクティビティを楽しんでいるかのような、そんな楽しい雰囲気が漂っていた。佐藤は次のように話す。
「一緒に作業をしながら、あるいは休憩時間をともに過ごしながら、私は多くの作業者たちとお話をさせていただいたのですが、これまで農業と関わりのなかった人たちから、『楽しい!』『また、やりたい!』という声を聞けたときは、本当に勇気づけられる思いがしましたし、それは生産者も同じでした。この取り組みは生産者のための労働力支援を目的としたものですが、私たちとしては作業員の満足も満たしていきたいと思っていたからです」
この発言の裏には、早見たち本所担当者の構想と、佐藤たち現場担当者の夢が隠されている。それというのも一連の取り組みは、単なる「労働力支援」ではなく、その先に「新規就業支援」を組み込んだ、国策とも合致する大義ある内容に仕立ててあるからだ。地方創生、地域活性化は国の最重要課題のひとつだが、それを実現するためには都市部からの移住者を増やす必要がある。さらに移住や、それにともなう転職は、すぐに決断できるものではない。そこで大きな意味を持ってくるのが今回の取り組み、言い換えるならJTBとの農業労働力支援事業であり、早見たちがJTBと組んだ本当の狙いも実はここにある。早見は解説する。
「佐藤さんたちが進めた山形での試験導入は、残念ながらコロナ禍ということもあり、求人も県内に留めました。でも、今後は求人を全国に広げたいと私たちは考えています。都市部に暮らす人たちが農村部に足を運んで農作業をする。そんな旅行があってもいいはず。対価も支払われるので交通費に充てられますし、『農泊』すれば滞在費も抑えられます。こうして都市部と農村部を往来してもらうだけでも地域経済は活性化しますし、そうやって農村部の暮らしを知ってもらえれば、移住に対するハードルも下がるかもしれません。完全移住は難しくても、テレワークが浸透し、副業も認められつつある今日においては、都市部と農村部の二地域居住も現実味を増しています。そうした人たちに対し、われわれの農業労働力支援事業は農作業という仕事を提供できるし、もし農業に転職するということであれば、そこはJAグループとして全面的にバックアップすることもできます」

早見たち本所担当者の構想とは、農業労働力支援事業をきっかけにして、人口の流動化を促し、移住へとつなげていくことで、地方創生、地域活性化を実現しようという、まさにこの国のあるべき姿を描いたグランドデザインそのものなのだ。

協同組合に根ざすJA全農だからこそ提供できる価値。
早見たちは現在、同じく労働力不足に悩む漁業や林業にも展開しようと、同じJAグループ内の農林中央金庫を介し、全漁連や全森連とも連携の話を進めている。こうして農閑期においても、漁業や林業で仕事を用意することができれば、作業者たちも安定して働くことができる。熟練ともなれば作業リーダーとして活躍してもらうこともできるし、特定の技術に精通した専門チームが結成されれば、その人たちを全国に派遣し、課題解決のためのソリューションを提供してもらうこともできる。もしかしたら、気心の知れた人たち同士で農業法人が立ち上げられる、そんな日も来るかもしれない。
こうした夢を次々と思い描けるからこそ、早見も差し迫る団塊世代の大量離農を目前に控え、1日も早く事業として全国に拡大させていきたいと思うし、取り組みが軌道に乗るよう、生産者、JAグループ、関係機関、そして何よりJTBをはじめとする各企業の協力を得ながら、地道に着実に業務を進めている。対して、佐藤たち現場担当者たちは、作業者たちと直接触れ合う機会もあるからこそ、その人たちの秘めた思いに心動かされ、思いを新たにするのだ。佐藤は、ある逸話を教えてくれた。
「今回の求人に応募してくださった人たちのなかには、フリーター、引きこもり、ニートと呼ばれる人たちも少なからずいました。そうした人たちの話を聞いていると、現代社会になかなか馴染めず、ひとり苦しんできた胸の内が痛いほどに伝わってきました。そこに資本主義の歪みを垣間見ることもありましたが、そうした人たちから『こうやって自分にも働ける場を用意していただき、本当にありがたいです』という言葉を聞いたとき、私はこの取り組みを、いろいろな人たちが抱える思いをすべて受けとめ、そっと背中を押してあげることもできる事業にしたいと、心の底から思いました」
前述の佐藤たち現場担当者の夢とは、まさにこれだ。農業の厳しさだけでなく、あらゆる人たちを等しく受け入れてしまう農業の懐の深さを知っている。だからこそ、農業を起点に多様な働き方を実現させ、誰もが活躍できる多様性のある社会へとつなげていきたい、そう思うのだ。そして農業労働力支援事業が、直接雇用ではなく間接雇用、作業者の自由な選択を可能にする「請負」の形を取っているのも、農業の復興や再生だけが目的ではなく、関わるすべての人たちの幸せにつなげていきたいと思っているからだ。まさに相互扶助の精神であり、協同組合に根ざすJA全農だからこそ提供できる価値である。
(文中の企業名、敬称略)